みなさんこんにちは!撮れ高映像部の西川です。
私は最近、とあるアーティストの全国ツアーの撮影業務をご依頼いただき、『画出し』や『サービス映像』と呼ばれる、会場内のスクリーンに映る映像を撮影を行うCA(カメラアシスタント)として参加しましたのでご紹介いたします。
この画出しの現場では、一日限りの単発で参加するといった、収録の現場とは異なる点があるため、その違いや現場の流れなどをご紹介していきます。
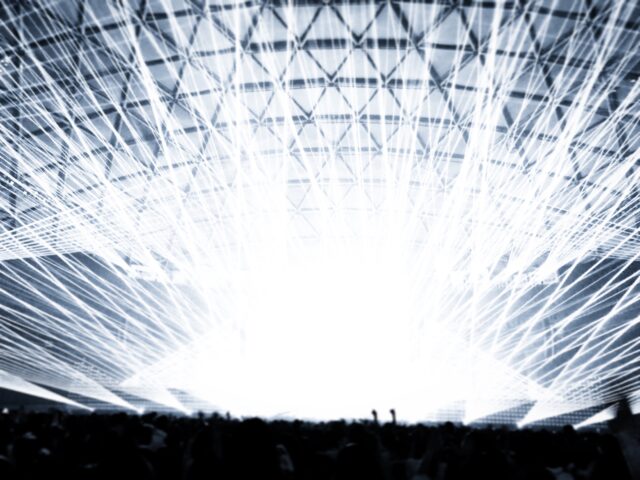
収録現場との違い①:時間的な余裕
まず始めに感じたのは、時間的な余裕です。今回のツアーでは仕込み日が2日間設けられており、カメラチームは仕込み日の2日目からの参加となりあmした。本番前日から準備ができるため、ある程度余裕を持って準備をすることができます。朝の集合も早朝ではなく朝9時頃ですが、例えば大阪公演だと、東京から始発の新幹線に乗って大阪入り、9時前に会場到着という流れであるため、4時起きで東京駅に向かうという辛さもありますが、福岡など東京からかなり遠い地方の公演になると、飛行機でその前日に入ることになるため、少し余裕があり嬉しく感じます。
収録現場との違いその②:スタッフの人員が少ない
収録の現場と比べて人数が少ないです。収録の現場の場合、そもそもカメラ台数が多いということもあり、カメラアシスタントの人数も余るくらいに居る事もありますが、今回のツアーの現場では、固定カメラも含めて10台というカメラ台数に対し、カメラマンは5人、カメラアシスタントは3人という体制でした。カメラマンさんにも準備を手伝っていただけるため、仕事は成り立ってはいるものの、これをカメアシのみで準備するとなると、かなり厳しいかもしれません。
ただし、同じメンバーで何公演も回っていくため、次第に次にやるべきことが分かってきます。そのため、公演回数を重ねるにつれ、準備・撤収にかかる時間が短くなっていくのも事実です。このようにツアーを回りながら、徐々に連携が取れて来る様子がとても面白いく遣り甲斐があると感じたポイントです。
会場での機材セッティングについて
今回、機材はLEDチームの機材と共にトレーラーで運送されていたため、私たちカメラチームが到着する仕込み日2日目には、既に会場内に機材搬入された状態です。この時点で、まだステージ周辺は音響さんが使用する機材が散らばっており、ケーブルやカメラを置ける状態ではないため、まずステージ上に配置するカメラを準備していきます。
今回、ステージ上ではドラムやキーボードの周りに、ポブカムやアクションカム(小型のビデオカメラ)を配置しています。そこから、電源ケーブルや同軸ケーブルなどをステージセット内に上手く這わせて、ステージ横の光伝送の元へ引いていきます。今回は360度観客席のセンターステージで、さらにその周辺がターンテーブルで回転するため、ステージ下に潜ってケーブルを引く必要がありました。
この時に大事なことは、きちんとケーブルにバミリやナンバリングをしておくことです。「サービス映像」と書いておくことで、撤収時に、ケーブルが万一どこかに行ってしまっても確実に戻ってきますし、ナンバリングをしておくことで、例えば「3カメの2番目のケーブルがまだ戻ってきていない」などとわかりやすくなります。特にステージ周辺は、あらゆる部署のあらゆるケーブルが入り乱れて引かれているため、こうした工夫が確実で素早い撤収につながります。セッティングの段階から撤収のことを考えておくことで、逆にセッティングの方も効率が良くなる部分もあるため、このような考え方は、他の現場でもしていきたいと感じました。
ステージ上のカメラのセッティングがひと段落すると、次はステージの前つらのカメラのケーブルを引いていきます。2台のカメラでステージの周りを行ったり来たりしながら撮影していくため、ケーブルもそれなりに長くなり、ケーブルを通し方次第で、本番中のケーブル捌きのやりやすさがかなり変わってきます。今回初めてセンターステージの現場に参加した事で、ケーブルの捌き方の引き出しを増やすことができるなど、とても良い経験ができました。
弊社は、コンサートやスポーツに関する各種イベントの画出し・撮影・収録の他、TV番組の収録、ENGロケ、ネット配信、PV撮影、映像制作など幅広く対応しております。まずは、お気軽に電話・メールにてご連絡下さい。
株式会社 撮れ高 (03-6274-8982)



